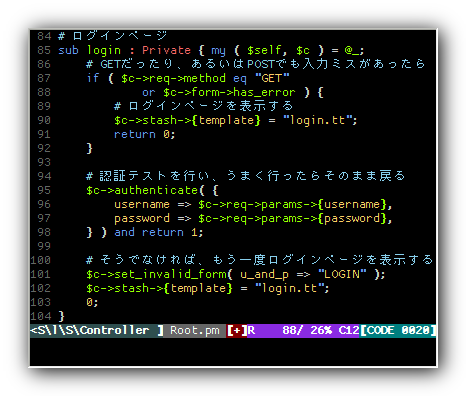備忘録。単独記事に書くまでもない小ネタ。
Perl 5.10で追加された予約語(“say”、“given ~ when”、“state”)などをワンライナーで使うときは“-e”の代わりに“-E”を使う。
$ perl -E 'say "Hello, World!"' Hello, World!
Perl 5.8だか5.10だかわからんときは、“-l”オプションを付けておくとprintがsayに変身するので便利。
$ perl -le 'print "Hello, World!"' Hello, World!
スクリプトの一行目(shebang)にオプションを書いても良い。
#!/usr/bin/perl -l print "Hello, World!";
これは「$\ = $/;」を本文に含むことと等価だ。そのため、「$/」特殊変数をいじるオプション(“-0”など)と共に利用するときは順番に注意しないといけない。
$ perl -e '$\ = $/; print "Hello, World!"' Hello, World!